
DRS
DRS(Drag Reduction System)とは、走行中にリアウイングの角度を可変させて空気抵抗を低減し、直線でのトップスピードを向上させるアクティブ・エアロデバイスのことを指す。日本語では「空気抵抗低減システム」といったところだ。
オーバーテイクの機会を増やすことを目的に、前年まで採用されていた可変フラップ付きフロントウイングに代わり、2011年に導入された。当初は可変リアウイングとも呼ばれていたが、次第にDRSの名称が定着した。なお、2026年のレギュレーション改定により、DRSは廃止され、代わってラップ中いつでも作動可能な「アクティブエアロダイナミクス」が導入される予定だ。
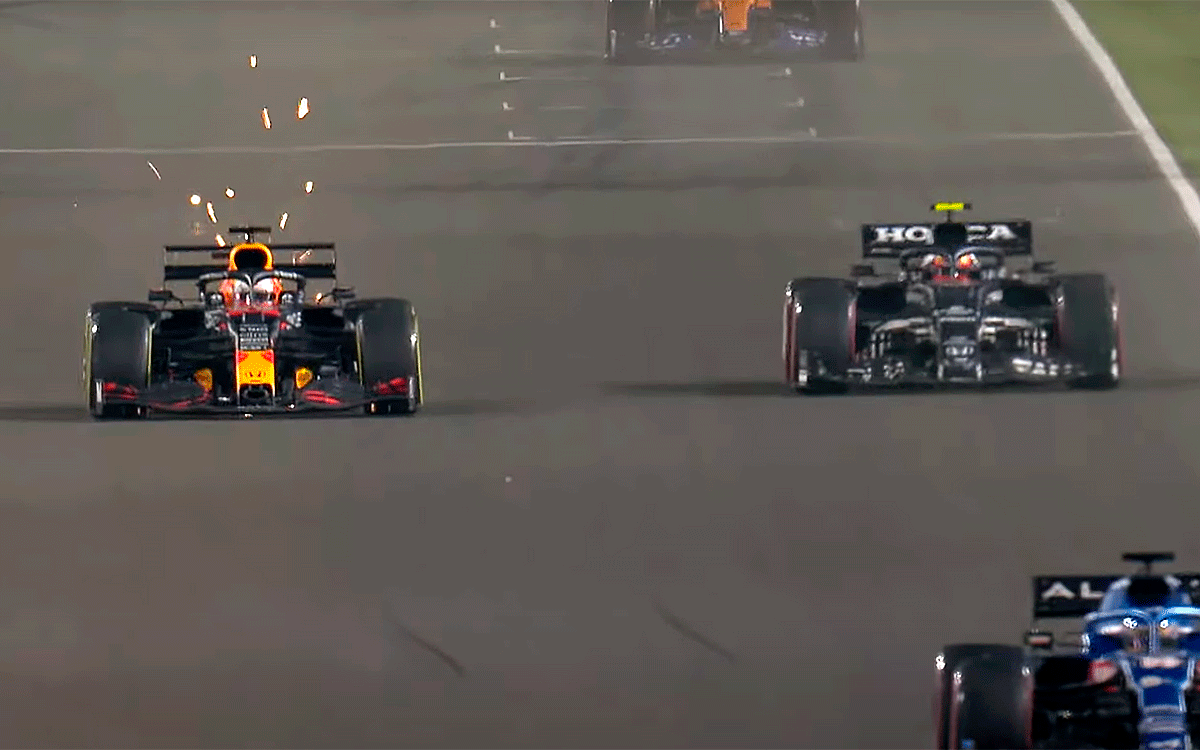 copyright FORMULA 1
copyright FORMULA 1
マックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)に抜かれたタイミングでDRSを稼働させるピエール・ガスリー(アルファタウリ・ホンダ)、2021年11月21日F1カタールGPにて
DRSの仕組み
レーシングマシンは一般的に、空力パーツによって生み出されるダウンフォースを使ってコーナリング速度を高めている。だがこうした空力パーツ、特にウイングには副作用があり、トップスピードを阻害する空気抵抗(ドラッグ)を発生させる。
高いコーナリング速度と、その代償としてのトップスピードの低下。この矛盾を解消するのがDRSだ。ステアリングに備えられたDRSボタンを押すことで、リアウイング上部のフラップが開き、空気が抜けやすくなって空気抵抗が軽減される。フラップは最大85mm(2018年以前は50mm)開閉可能で、「オーバーテイクウイング」とも呼ばれる。
コースやマシンの特性によって差はあるものの、DRS作動時と非作動時ではトップスピードに約10〜20km/hの差が生じることがある。特に向かい風の条件下では効果が顕著だ。
以下の動画では、ケータハムF1のチーフエンジニア、ジャンルカ・ピサネッロ氏と空力責任者ハリ・ロバーツ氏が、DRSの物理的な動作を解説している。
DRSの使用ルール
DRSの使用には厳格な条件が設けられている。以下が主なルールだ。
- 使用可能区間(DRSゾーン)は各サーキットに予め設定されている
- DRS検知ポイントにおいて、前車との差が1秒以内だった場合にのみ作動可能
- ウェットコンディションや視界不良時には作動不可
当初は、各サーキットのメインストレート終端600m区間においてのみ使用を許可するルールであったが、導入2戦目となった2011年オーストラリアGPを前に調整が行われ、現在では各サーキット毎に1〜4か所の「DRSゾーン」が設けられている。
ゾーンの手前には「検知ポイント(ディテクションポイント)」があり、ここで前車との差が1秒以内でなければ、ゾーン内でも使用は許可されない。ただし、フリー走行および予選セッションでは、ゾーン内で自由に使用できる。
DRSの詳細な規定についてはF1レギュレーションDRS編を参照。
DRSの運用トラブル
2019年最終戦アブダビGPでは、データサーバーの不具合により17周目までDRSが作動しないトラブルが発生した。これは2011年の導入以来初の事例で、F1とFOMが共同管理する検知システムの中枢が一時的にダウンしたことが原因だった。
ミニDRS
2024年のアゼルバイジャンGPでは、マクラーレンのリアウイングのフラップが高速走行時にたわみ、空気抵抗を減らす仕組みが備わっていることが明らかとなり、一部で「ミニDRS」と呼ばれた。
この技術には2つの方法が考えられている。一つはカーボンファイバーの積層構造と素材の組み合わせにより、特定速度域で剛性が変化するよう調整する方法。もう一つは、車体の沈み込みを利用してリアウイングの取り付け角度を変化させる方法だ。いずれもレギュレーションのグレーゾーンを突いた設計といえる。


















