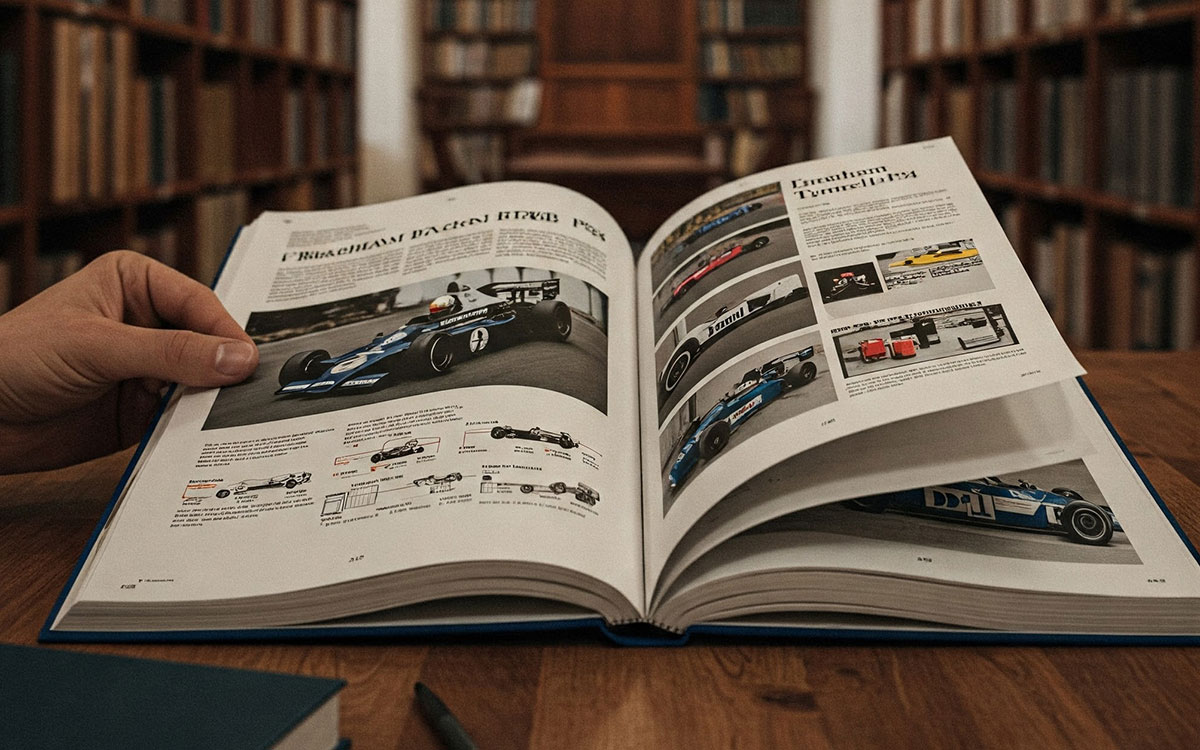
革新か、禁じ手か? 画期的技術で振り返るF1史―競争が生んだイノベーションの軌跡とその規制
F1の技術革新はモータースポーツの枠を超え、自動車工学や現代社会に大きな影響を与えてきた。F1で生まれた技術の多くは、公道車両や他の産業にも応用され、私たちの生活に密接に関わっている。
本記事では、「画期的な技術」という観点から、75年にわたるF1の技術進化を5分ほどで振り返る。
ミッドシップ革命—クーパーの挑戦
1946年の創設以来、F1はエンジニアリングと技術革新の最前線を走り続けている。特に1950年代には、アルファロメオ、フェラーリ、マセラティといったメーカーがより強力なエンジンを開発し、1951年にはアルファロメオ159が400馬力の壁を突破した。しかし、この「パワー競争」に革命をもたらしたのが、小さなガレージで作られた1台のクルマだった。
 creativeCommons David Merrett
creativeCommons David Merrett
1958年型F1マシン「クーパーT43」、2011年7月22日シルバーストーン・クラシック2011
1957年、チャールズ・クーパーと息子のジョンが開発したクーパーT43は、F1史上最も影響を与えたクルマの一つとされる。わずか190馬力のコヴェントリー・クライマックス製4気筒エンジンを搭載しながら、T43は初めてエンジンをドライバーの後方に配置したミッドシップレイアウトを採用した。
この革新的な設計は、1958年のアルゼンチンGPでスターリング・モスがT43を駆り、F1初のミッドシップ車による優勝を果たしたことでその真価が証明された。その後、モナコGPでモーリス・トランティニアンがさらに勝利を重ねたことで、他チームもこの新コンセプトを追従した。
1959年と1960年にはクーパーがドライバー&コンストラクターズタイトルを獲得し、ついにはフェラーリも1961年の「156F1 」にミッドシップレイアウトを採用。F1の歴史がこの瞬間から大きく変わった。
初期のF1マシンはフロントエンジンが主流だった。ミッドシップは車両の重量バランスを改善し、ハンドリング性能を大幅に向上させた。クーパーT43の台頭により、1960年代にはすべてのF1チームがミッドシップレイアウトへ移行。レースカーの基本設計として定着した。
モノコック構造—ロータスの革命
 creativeCommons Georg Sander
creativeCommons Georg Sander
1962年型F1マシン「ロータス25」、2013年7月13日
1962年、ロータスの創設者コーリン・チャップマンはさらなる革新をもたらした。ロータス25は従来の鋼管フレームを廃止し、モノコックシャシーという革新的な構造を採用。これにより車体剛性が飛躍的に向上し、重量も大幅に削減された。
鋼管フレーム構造は、複数の鋼管を組み合わせたフレーム方式で、製作が比較的容易で修理もしやすい一方、接合部の強度や重量面での課題があった。対してモノコック構造は、車体全体を一体成型する設計で、荷重を均一に分散し、軽量かつ高い剛性と安全性を実現した。
ロータス25は1962年から1965年まで使用され通算14勝を記録。1963年と1965年にはダブルタイトルを制覇した。モノコックシャシーはすぐにF1のスタンダードとなり、今日のF1マシンの基本構造に受け継がれることとなった。
さらに1981年には、ロータス88に世界初のカーボンファイバー製モノコックが採用された。ただ、実戦投入されなかったため、カーボンファイバー製モノコックを採用した世界初のF1マシンとしては、マクラーレンMP4/1の名が知られている。
異端のアイデア—6輪車とファンカー
1970年代には、一風変わったアイデアも登場した。その代表例がティレルP34である。
 creativeCommons David Merrett
creativeCommons David Merrett
1976年型F1マシン「ティレルP34」、2012年7月22日シルバーストーン・クラシック2012
1976年に導入されたこのクルマの狙いは、前輪を4輪とすることで空力性能を向上させる点にあった。ドラッグ低減のためにフロントタイヤが小径化され、これに伴う接地面積の減少分を4輪とすることで補った。
スウェーデンGPではワン・ツーフィニッシュを達成するなど一定の成功を収めたが、定着するには至らなかった。
6輪構成は4輪構成に比べてサスペンションやブレーキなどのシステムが複雑で、開発・調整、修理の面で難があった。また、開発コストや技術リソースの面での負担も大きく、空力面での理論的な優位性はありながらも4輪マシンと比べて決定的な差別化が図れなかった。
 creativeCommons edvvc
creativeCommons edvvc
1978年型F1マシン「ブラバムBT46B」、2001年7月グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード
また、1978年にはブラバムが「BT46B」を投入した。後部に大型のファンを搭載したこのマシンは「ファンカー」と呼ばれた。
通常、ファンはエンジン冷却などの目的で用いられるが、BT46Bではこのファンを主に空力、つまり車体下部の空気を吸引して低圧状態を作り出し、自然なグラウンドエフェクト以上のダウンフォースを生み出すために利用された。
ブラバムBT46Bは1978年のスウェーデンGPで初登場し、ニキ・ラウダが圧倒的な勝利を収めたが、現行の技術規定の隙間を突いた革新的な設計であったため、他チームから「ルールの精神に反する」との批判が上がり、わずか1戦でお蔵入りとなった。
BT46Bは、技術革新とレギュレーションとの境界線に挑む姿勢の象徴ともいえる存在だった。短命に終わったとは言え、F1における技術革新の可能性と限界を示す重要なマイルストーンとなった。
ターボ時代の到来
 creativeCommons
creativeCommons
1977年型F1マシン「ルノー RS01」、2018年7月13日
1977年、ルノーによってF1史上初のターボエンジン車「RS01」が投入された。当初はターボラグや急激なパワーデリバリー、燃料・冷却システムの管理といった新たな課題に直面し、「黄い煙突」とも揶揄された。
それでもなお、小排気量でありながら従来の自然吸気エンジンを超える可能性を示した。ルノーはRS01で得た知見を基に、エンジンマネジメントや冷却システム、空力パッケージの改良を重ね、ターボエンジンを競技で有利に働かせるための基盤を構築。1979年フランスGPで後継の「RS10」がついに初勝利を挙げた。
この成功により、1980年代にはターボ時代が到来。フェラーリ、ホンダ、BMWなどが1,000馬力を超えるターボエンジンを開発し、F1はパワー競争の新時代を迎えた。
なおRS01が導入されたのと同じ1977年には、ロータス78が「グラウンド・エフェクト」を活用。形状を工夫して車体下面に負圧を発生させることで、高速時の安定性を飛躍的に向上させた。これによりコーナリングスピードが劇的に向上し、F1マシンの性能が一変した。
電子制御技術の台頭—アクティブサスペンション
1980年代後半、F1では電子制御技術の進展とともに、各チームがマシン性能の向上のために「電子ドライバー補助システム」を積極的に研究・採用し始めた。
特に、1992年のウィリアムズ「FW14B」は、アクティブサスペンション、トラクションコントロールなど、当時としては革新的な電子制御技術を多数搭載し、「ドライブ・バイ・コンピューター」の象徴的な存在となった。
アクティブサスペンションとは、電子制御により車高やサスペンションの硬さをリアルタイムで調整する技術で、路面状況に応じて最適なセッティングを維持することができる。
 Courtesy Of Williams
Courtesy Of Williams
1992年のウィリアムズFW14Bをドライブするナイジェル・マンセル、2022年6月26日グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードにて (1)
パトリック・ヘッドとエイドリアン・ニューウェイの叡智が注がれたFW14Bを手にしたナイジェル・マンセルは、圧倒的な速さでシーズンを支配し、ウィリアムズはダブルタイトルを獲得した。
しかしながら、1994年にFIAはアクティブサスペンションを含む電子補助システムの使用を全面的に禁止した。その背景には、技術の複雑化とコストの高騰により、資金力のあるチームとそうでないチームの間に大きな格差が生じたこと、また、ドライバーの技量がシステムに依存しすぎることへの懸念が巻き起こったことが挙げられる。
以降、F1マシンのサスペンションは従来の受動的なものへと戻り、ドライバーのテクニックに再び焦点が注がれるようになった。
画期的な技術とその規制
F1において革新的技術はDNAそのものだが、一方で、それらが競争の公平性や安全性の観点から規制されることもある。
レッドブルは2010年、排気ガスをディフューザーに吹き付けることでダウンフォースを増大させる技術「ブロウンディフューザー」を生み出し、大きな優位性を確立した。しかし、空力依存の高まりが安全性の懸念を引き起こし、2011年以降段階的に規制された。
 creativeCommons Jose Mª Izquierdo Galiot
creativeCommons Jose Mª Izquierdo Galiot
2010年型F1マシン「マクラーレンMP4-24」、2009年3月10日
同じ年にマクラーレンは、MP4-24に「Fダクト」を搭載した。これは、ドライバーがコクピット内のダクトを膝で操作し、リアウイングに向かう空気の流れを制御。ストレート走行中にドラッグを低減することを目的としたものだった。
通常、リアウイングは空気の流れを利用してダウンフォースを発生させる。Fダクトはこの流れを「遮断」または「撹乱」することで、直線走行時にウイングの効果を一時的に減少させ、最高速度を向上させる。
他チームもこれに追従したが、安全性の観点から2011年に禁止された。
近年では、2020年にメルセデスがデュアル・アクシス・ステアリング(DAS)を導入した。これは、ドライバーがステアリングを前後に動かすことで前輪のトー角を調整し、タイヤ温度管理を最適化する技術であったが、2021年シーズンに禁止された。
F1の未来—革新は止まらない
F1は常に技術革新の最前線にあり、これまでの75年間でその姿は劇的に変化してきた。今後も新たな技術が登場し、スポーツだけでなく、自動車産業や日常生活に影響を与えることは間違いない。













